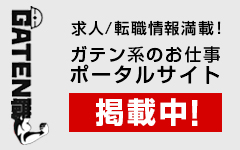みなさん、こんにちわ。松田建設工業 広報担当です。 ようやく夏の残暑も終わりましたね。今年の夏は、ほんとうに長かった(-_-;) 夏が、5月のゴールデンウイークから始まり、10月も終わろうとしているのに先週まで半袖が活躍した事に驚きです。秋って9月下旬から11月中旬ごろだと思うんですが、秋が短いと思いませんか? カードゲームでようやく自分に順番が回って来たと思ったらスキップや逆回転で疎外感を感じるさまに似てますよね。秋が拗ねてしまって寒い冬が飛び越してやって来ました。
そんな寒暖差を感じる現場作業の大事な一歩は、図面に記載されている設計数値のやり方を出す事です。
全ての作業の基準となるやり方(丁張)は、現場測量を行い構造物の位置と高さを求める事から始まります。測量はすべての工事の基準となる作業です。
何もない地面に座標から求めるポイントを測量機と計算で基準点を出すスペシャリストが測量士です。測量士の仕事は、学校で習った数学が仕事に活用される仕事です。
測量士が出した基準点を基点にして、工事を進める設計図を現場に描く作業が現場測量のやり方(丁張)・墨出です。
やり方(丁張)は、掘削や盛土など土木作業で使用される事が多い基準です。設計図の線を水糸と呼ばれる強度の強い糸で位置と高さを表します。この水糸を結びつける門型のものがやり方(丁張)呼ばれるものです。
墨出とは、コンクリートに墨壺を使用して設計図の通り芯や基準高を表す基準線を出す作業です。建築構造物に使用されて多種多様な業者が墨出の基準に基づいて高層ビルなどの巨大建造物の施工に活用されています。
今回は、外構工事で活用されるやり方(丁張)を紹介したいと思います。
現場で活躍する測量機です。
 左からオートレベル、回転レーザーレベル、トータルステーション、墨出レーザー
左からオートレベル、回転レーザーレベル、トータルステーション、墨出レーザー
左の2台は、高さを計測する機器で右の2台は直線を出す機器です。トータルステーションには、角度X軸・Y軸の角度調整も備わっていて角度を含めた測量も可能です。 その他にも光波測定器と呼ばれるトータルステーションに距離を求める機能が付いた測量機器もあります。測量機器とパソコンや重機を連携させて施工技術のIT化も現場ではドンドン活用されつつあります。
やり方(丁張)は、測量杭を打ち込み、オートレベルや回転レーザーを使って任意の設計高さを測量して測量杭に印を付けて胴縁を打付けて門型に組みます(下記、写真)

やり方は、高さと共に通りと呼ばれる直線も明示されます。やり方を基に行わる作業としては、掘削・床付作業・基礎砕石敷均し作業・コンクリート打設作業・縁石などの二次製品据付作業・雨水排水などの配管布設作業・盛土・法面整形など多種多様な用途に使用されます。


作業する上で非常に重要なやり方ですが、高さと通りを明示させる技術なので測量機器の使い方、測量技術の理解、図面に書かれてる数値を理解できれば未経験者でもやり方を作成する事はすぐに出来るようになります。
しかし、同じやり方であっても仕事の先読みが出来るベテランや仕事を良く知る現場監督とでは、工夫と利便性などが大きく異なり実際に作業を行う職人がより仕事を進める事が出来るようなやり方を作成します。
例えば、重機を使う掘削作業では重機の移動で邪魔にならないように張り出し型のやり方を作成や通り線が交差したり折れ点などが水糸で分かるような位置にやり方を作成したり、余堀を含めた線を明示したりと工夫次第で作業の進捗状況が変わります。
やり方の作成だけをとってみても、仕事が出来る人、経験が浅い者でも仕事を考えている人だと見抜く材料が現場には転がっています。
現場作業は、仕事を楽しめるコツが多く広がっています。これからも現場作業が楽しい理由を紹介したいと思います。
それではみなさん、ご安全に。


 左からオートレベル、回転レーザーレベル、トータルステーション、墨出レーザー
左からオートレベル、回転レーザーレベル、トータルステーション、墨出レーザー